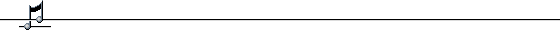Opinion : 「All or Nothing」と「中庸」の使い分け (2002/7/8)
例の「脱ダム宣言」がきっかけになったゴタゴタなのか、長野県知事の不信任騒動というのが起きているそうだ。ここのところ多忙で、いささか世情に疎くなっている私でも、このニュースぐらいは知っている。
ダム建設の是非は一概に論じられないので措いておくとして、この件に限らず、この国では物事を論じるのに、どうして何事も往々にして「両極端」に走りがちなのだろう、と思う。
たとえば、新幹線や空港、高速道路の建設がそうだ。膨大な資本を投下しても、元が取れるのであれば、それは造る価値があるし、現時点で明らかにキャパシティ不足になっているものを放置するのは、むしろ損失を生んでいるという見方もできる。
問題なのは、需要の有無とは無関係に、「1 県 1 空港」とか「整備新幹線計画」といった杓子定規な標語が一人歩きすることにあるのではないのか。需要がなくて、資本を投下しても回収できる見通しが立たないのであれば、無理して空港や新幹線、高速道路を造るのは無駄だ。
代わりに、在来線の高速化とか、国道の改修とか、飛行機と鉄道、あるいは高速道路の連携によって全体的な底上げを図るとか、そういった、コストパフォーマンスに優れたソリューションの方がいい。空港も高速道路も新幹線も、「フル規格で作る」vs「何も造らない」という、All or Nothing な考え方で論じるから、話がおかしくなる。フル規格より見劣りしても、今より高速化できて、費用もそれほどかからないソリューションがあれば、それを採用する方が最終的な成果は向上するはず。なのに、「国土の均衡ある発展」という錦の御旗を掲げて「フル規格」にこだわるのは、何か間違ってないだろうか。
田中知事の「脱ダム宣言」も然り。まあ、「公共事業のネタがなくなる」ということで「脱ダム宣言」に反対する側もどうかと思うが、「ダムならすべて反対」というのも、これまた All or Nothing。「個別に評価して、必要なら作る、不要なら止める」という判断の方が、よほど現実的ではないかと思うが、どうだろう。
もっとも、「必要なら作る、不要なら止める」という考え方が正常に機能するには、何か客観的な線引きが必要で、それはそれで難しい。かつて、国鉄ローカル線廃止論議の時には、輸送密度に「2,000 人」という線引きをしたせいで、いろいろと悲喜劇が起きた。とはいえ、数字の是非はともかく、このように明快な基準を示した上で、是々非々で決定するやり方は、理に適っていたと思う。
もし「脱・赤字線宣言」なんてやった日には、国鉄は山手線と新幹線以外、全部の線路をまくらなければならなかったところだ。この「All or Nothing」という考え方は、適用すべき場面と適用すべきでない場面がある。そこのところを間違えているケースが少なくないのが、最大の問題点だと思う。
たとえば、犯罪捜査や量刑の適用において情状酌量がはびこり過ぎると、収拾がつかなくなる。かつて、五・一五事件の後などに「彼等のやったことはよくないが、その心情を考えると情において忍びないから極刑は避けたい」なんていう論調があったらしいが、とんでもない話だ。
刑事犯については、刑法で「何をやったら何の刑を何年」と決められている。だから、裁判で量刑を決める時にもそれを遵守するのが大原則で、是々非々の判断だの、個人の裁量だのは入り込むべきではない。もし、判断基準を変えるというなら、そのときこそ国会が立法府として機能して、論議を尽くした上で変えればいい。それが民主主義国家・法治国家のあり方というものだ。
時代の変化に伴って、何か既存の法律では決められていない問題が出てきたら、それだって国民の代表によって審議した上で、明快な基準を決めるのが当然のこと。それをやらないのは、憲法に定められた三権分立に対する冒涜だ。逆に、先に引き合いに出した公共事業系の話や、あるいは歴史認識の問題なんていうのは、「All or Nothing」でやったら収拾がつかなくなる。公共事業についてはすでに触れたから措いておくが、歴史認識や国防をめぐる議論を見ても、どうしてどいつもこいつも、話が両極端に飛ぶのか。
右も左も、たとえば太平洋戦争については「全面肯定」vs「全面否定」、国防論議にしても「自主防衛・強力な軍備を」vs「非武装中立」。これでは話がかみ合うはずがない。本当の落としどころは、両者の中間あたりにあると思うのだが。
この手の個人の主観に大きく依存する問題では、どちらか一方にベッタリ寄った結論を出すのは難しいし、それはやってはいけないと思う。そういうときこそ「中庸」のセンスが求められるのだが、特に日本では、その「中庸」が嫌われるのは、どうにかならないのだろうか。
(そのくせ、中途半端にすべきでないところで「中庸」を発揮してしまうのだから、さらにタチが悪い)湾岸戦争のときに米陸軍第 VII 軍団の指揮を執っていたフレッド・フランクス中将 (湾岸戦争当時。退役時は大将) は、トム・クランシーとの共著「Into the Storm A Study in Command (邦題 : 熱砂の進軍。原書房刊) 」の中で、こんなことをいっている。
「戦うからには、100 対 0 が戦場における望ましい得点差だ。日曜午後の NFL のアメフトの試合なら 24 対 21 というスコアでもよいかもしれないが、戦場ではだめだ」
「敵が AK-47 銃で一発撃ってきたら、こちらの全火力を使って反撃した。あらん限りの火力で敵を攻め、むこうが一発撃ったこと自体を後悔させるようにしたものだ」まさに「All or Nothing」の究極だが、これはあくまで、話し合いでけりが付かず、戦わざるを得なくなった時の話。話し合いで何か実のある結論を出すには、「中庸」や「妥協」が必要になることがほとんどだと思う。
しかし、相手に妥協するつもりがなく、刃を交えるとなったら、それはまた事情が違う。私自身、この、フランクス将軍の「100 対 0 主義」に激しく影響された一人なので、もし戦わざるを得なくなった場合には、あらん限りの手段を総動員して攻め立て、敵を完膚なきまでに叩きのめす (少なくとも、叩きのめそうとする) のをモットーにしている。
ただし、この「百対零主義」あるいは「All or Nothing」な考え方は、それを発動すべきときと発動すべきでない時の区別があるということを、忘れないようにしたいと思う。
Contents HOME Works Diary Defence News Opinion About
| 記事一覧に戻る | HOME に戻る |